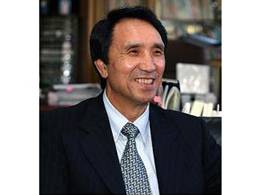遺産分割協議書とは・必要性と作成方法をわかりやすく解説
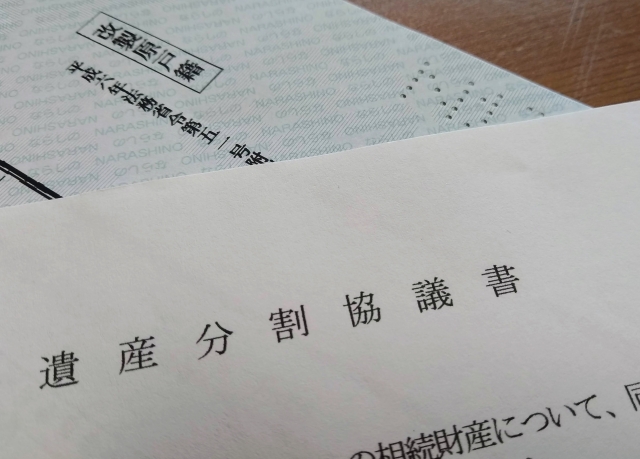
被相続人(故人)が遺言書を残さず、遺産分割に関する取り決めを相続人で行う必要がある場合は、「遺産分割協議書」を作成します。
これは遺産分割協議で相続人が合意に達した内容を書面化したものです。
この記事では、遺産分割協議書が必要なケースや、作成の流れ等について解説します。
遺産分割協議書とは何か
遺産分割協議書は、相続人同士で話し合い、合意した内容をまとめた書類です。
遺産分割を協議するときは相続人全員が参加しなければいけません。
協議では誰が被相続人の預金・不動産を引き継ぐかや、相続の割合についても取り決めます。
協議で相続人全員の合意に達した後、取り決めた内容を文書化するため、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書の書式は自由に作成して構わないものの、相続人全員が署名・押印(実印が好ましい)しなければいけません。
また、遺産分割協議書には印鑑登録証明書を添付したうえで、相続人全員が同じ内容の遺産分割協議書を1通ずつ所持します。
遺産分割協議書が必要か否か
遺産分割協議書の作成は相続の内容によって必要となったり、行わなくてもよかったりする場合があります。
必要となるケース・不要となるケースをそれぞれみてみましょう。
(1)遺産分割協議書が必要な場合
遺産分割協議書の作成は、主に相続人や被相続人の遺産が多い場合、相続登記や相続税申告の手続きを行う場合に必要となります。
①相続人が複数いて、遺産が多い
次のような場合に遺産分割協議および協議書の作成が必要です。
- 被相続人の配偶者の他、子どもが4人いるというように相続人が多く、各相続人が納得するように慎重な分割協議が必要
- 被相続人が現金・預金のような金融資産の他、複数の土地建物を有していて、相続人がどのように分けるか話し合う必要がある
ただし、遺産が現金・預金のような金融資産だけなら、相続人が多くいても均等に分けやすいので、遺産分割協議および協議書の作成は不要となる場合があります。
②相続人同士のトラブルを防ぎたい
相続人が少なく、被相続人の遺産が多くなくとも、相続人同士のトラブルを避けるため、協議書の作成をした方がよいケースもあります。
例えば、以下のようなケースです。
- 相続人同士の仲が悪く、遺産分割協議書を作成しないと互いに安心できないとき
- 特定の相続人が被相続人の生前に財産を与えられ(特別受益)、それに配慮した遺産分割を話し合いたいとき
「特別受益」とは、特定の相続人が被相続人からの遺贈・生前贈与で特別に得られた利益です。
特別受益を得られた相続人がいた場合、相続開始時、他の相続人と均等に遺産を分けると、逆に不公平な分割となるおそれがあります。
そのため、特別受益を受けた相続人に対し、相続時に特別受益の分を差し引き、遺産分配する旨を取り決めるため協議書の作成が必要となるのです。
遺産分割協議書を作成していれば、特別受益を受けた相続人から後日、「そんな取り決めをした覚えはない」と協議した内容を否定されるおそれもありません。
③相続登記や相続税申告の手続きが必要である
相続手続きを進める中で、遺産分割協議書を必要とする場合もあります。
例えば、以下のようなケースです。
- 複数の相続人がいる中で、被相続人の不動産を単独で相続する
- 相続税の申告時に、相続税軽減のため特例等を活用する
被相続人の不動産を単独で相続する場合、相続登記を進めるには、他の相続人が同意した事実を法務局に証明しなければいけません。
その証明に遺産分割協議書を利用します。
ただし、遺言書で不動産の相続人が指定されているとき、法定相続分で他の相続人と共有取得するときは、遺産分割協議書がなくても登記は可能です。
一方、相続税が発生する場合に税を軽減できる特例等の利用時も、遺産分割協議書が必要です。
例えば、以下の特例を利用するとき、協議書を準備しなければいけません。
- 小規模宅地の特例:被相続人の住居等を相続するとき相続税評価額が最大80%減額できる特例
- 配偶者の税額軽減:配偶者であれば大幅に相続税が減税できる特例
ただし、上記の特例を利用する場合でも、遺言書があれば遺産分割協議書は不要となります。
(2)遺産分割協議書が必要ない場合
相続人が一人だけやごく少数、被相続人の作成した遺言書がある等という場合、作成は不要です。
①相続人が一人だけ
例えば、相続人が自分だけ、または自分と弟の二人だけというケースです。
自分一人ならば被相続人の遺産すべてを相続できるので、そもそも作成の必要性はありません。
また、相続人が二人だけで、法定相続分で分割可能という場合も作成は不要です。
ただし、相続人の仲が悪く、互いに不信感を持っている場合は文書化した方がよいでしょう。
②遺言書がある
被相続人(遺言者)の作成した遺言書があるなら、遺言書で記載された内容に従い、遺産を分配するのが一般的です。
ただし、遺言書の内容に相続人の一部または全員が不満であれば、全員の合意により、改めて遺産分割協議で決めなおしても構いません。
③法定相続分で分割する
相続人が民法で定められた法定相続分(民法第900条)に従って遺産分割を行うならば、協議書の作成は不要です。
例えば、被相続人の遺産が主に預金なので分割しやすい場合や、相続不動産を法定相続分に応じて共有取得する場合があげられます。
遺産分割協議書の作成方法について
遺産分割協議書の記載内容や書式等は法定されているわけではありません。相続人同士が自由に遺産分割内容を取り決め、手書きやPCで作成が可能です。
ただし、第三者からみて有効な遺産分割協議書と認められるためには、遺産分割内容の正確な記載および署名・押印をする等、慎重な作成が求められます。
(1)遺産分割協議書の作成手順
遺産分割協議書を作成する前に様々な作業が必要となります。作成までの流れは次の通りです。
- 遺言書の有無を確認し、被相続人の財産調査を開始
- 相続人が誰かを確認
- 相続人全員で遺産分割協議を行う
- 遺産分割協議書を作成
まず遺言書を残しているかどうかについて確認しましょう。
被相続人が遺言書を保管していそうなデスクや金庫、公正証書遺言を作成している可能性があるなら公証役場で確認します。
遺言書がなければ被相続人の財産を調査し、遺産総額や負債がどれくらいかを把握します。
その後、被相続人の本籍地の市区町村役場から戸籍謄本等を取得し、法定相続人を確定しましょう。
なお、被相続人に離婚歴があり前婚の子どもがいる場合は、その子どもは相続権を有しているので注意が必要です。
相続人全員で遺産分割協議を行う場合、対面で協議するのはもちろん、電話やオンラインで話し合う方法も有効です。
協議で取り決めた内容に相続人全員が合意したら、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名・押印します。
遺産分割協議書は同じ内容のものを相続人分作成しましょう。
ただし、相続人分の作成が難しいならば、相続人全員の署名押印後の原本をコピーし、各相続人に配布する方法もあります。
遺産分割協議書を作成した後は、相続人である事実を証明する「戸籍謄本」、相続人全員の「印鑑登録証明書」とともに保管しておきましょう。
(2)遺産分割協議書の作成ポイント
遺産分割協議書を作成するときは、次の内容を明記しましょう。
- 被相続人の氏名・最後の住所・死亡日
- 相続人全員が遺産分割方法・割合に合意している旨
- 相続人が分割する相続財産の具体的内容
- 相続人全員の氏名・住所・押印(実印が好ましい)
遺産分割協議書に押印する場合、実印を使用した方がよいです。
なぜなら、認印を使用すると法務局や金融機関は「相続人が同意したと認められない」と判断し、窓口で手続きを拒否されてしまう可能性があるからです。
(3)遺産分割協議書の記載例
具体的な記載例は次の通りです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
遺産分割協議書
令和7年7月5日、〇〇市〇〇町〇〇番地、〇〇〇〇(被相続人氏名)の死亡によって開始した相続の共同相続人である配偶者〇〇〇〇と、子〇〇〇〇は、本日、その相続財産について、次の通りに遺産分割することへ合意した。
1.相続人である配偶者〇〇〇〇は次の遺産を取得する。
【土地】
所 在 〇市〇町〇丁目
地 番 〇番〇
地 目 宅地
地 積 250.00㎡
【建物】
所 在 〇市〇町〇丁目
家屋 番号 〇番〇
種 類 居宅
構 造 木造瓦葺2階建
床 面 積 1階 120.00㎡
2階 60.00㎡
2.相続人である子〇〇〇〇は次の遺産を取得する。
【現金】 金20,000,000円
【預貯金】 ○○銀行○支店 普通預金 口座番号○○○○
3.本協議書に記載のない遺産及び後日判明した遺産については、相続人である配偶者〇〇〇〇がこれを取得する。
以上のとおり、相続人全員による遺産分割協議が成立したので、本協議書を2通作成し、署名押印のうえ、各自1通ずつ所持する。
令和7年7月5日
住所 〇〇市〇〇町〇〇番地
氏名 〇〇〇〇 実印
住所 〇〇市〇〇町〇〇番地
氏名 〇〇〇〇 実印
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
なお、遺産分割協議書は最初から自分で作成しなくても、無料で雛形をダウンロードできます。
参考:bizocean「遺産分割協議書」 の書式テンプレート・フォーマット
遺産分割協議書を作成するときの注意点
遺産分割協議書の作成期限は法定されていません。
しかし、相続税が発生するケースを想定し、相続税の申告期限(相続開始の事実を知った日の翌日から10か月以内)までに作成しておきましょう。
ただし、遺産分割協議書を作成しても無効となってしまうケースはいくつか存在します。
(1)遺産分割協議書が無効となるケース
遺産分割協議書が無効となり、協議をやり直さなければいけないケースは主に次の通りです。
- 相続人全員で遺産分割協議をしなかった、または相続人以外の人が協議に参加した
- 遺産分割協議のとき詐欺・強迫・錯誤があった
- 相続人の中に未成年や認知症の人がいた:協議の前に、未成年には特別代理人を、認知症の人には成年後見人等を選任し、協議のときに参加させなければいけない
遺産分割協議をやり直すよう他の相続人に求めても応じない場合は、最終的に裁判所へ「遺産分割協議無効確認訴訟」を提起し、協議の無効を主張していきます。
もし遺産分割協議書作成後に新たな遺産が出てきたら、以前の協議書は無効とならず、新たな遺産の分割方法のみを決めます。
なお、新たな遺産が見つかる事態を想定し、協議書に「新たな遺産が見つかった場合、相続人〇〇が取得する」と明記する方法も有効です。
(2)遺産分割協議書の作成に不安があれば専門家へ任せよう
遺産分割がやや複雑となってしまい、「自分の力で遺産分割協議書を作成するのは難しい」と感じたら専門家に相談してみましょう。
遺産分割協議書の作成は、弁護士、司法書士、行政書士等に任せることが可能で、費用の目安は3万〜10万円程度です。
遺産分割協議の取り決めを踏まえ、専門家と相談しながら、スムーズに作成を進めていけることでしょう。
まとめ
遺産分割協議および協議書の作成は、相続人同士で自由に取り決めができます。
しかし、遺産分割協議に不備があると協議書も無効になってしまいます。
また、遺産分割協議書の内容が不明確なら、法務局・金融機関等の窓口で手続きを拒否されてしまうことでしょう。
遺産分割協議書の作成に不安があれば、事前に相続問題に詳しい専門家に相談することをおすすめします。