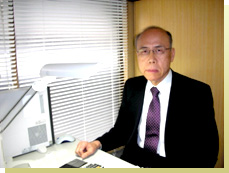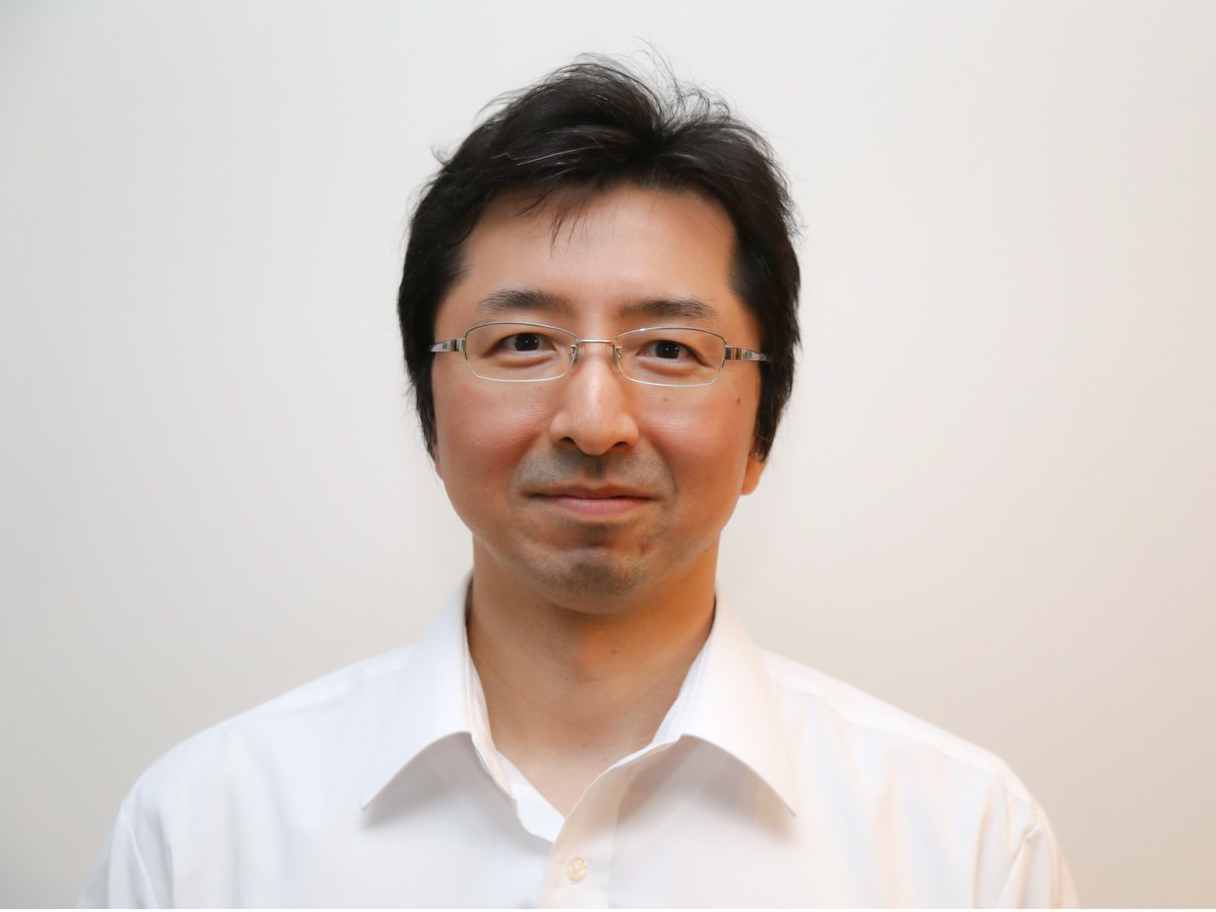不動産相続でよくあるトラブル事例と解決方法を解説

被相続人の遺産の中には不動産も含まれているケースがほとんどです。法定相続人が1人または2人の場合、誰が引き継ぐのかは決めやすいでしょう。
しかし、法定相続人が多い場合や、相続する不動産を誰も引き継ぎたくないときは、相続人の間でトラブルに発展する可能性があります。
この記事では、不動産相続で揉める可能性が高いケース、トラブルの解決方法などについて解説します。
不動産相続で揉める可能性が高いケース
被相続人から不動産を相続した場合、必ずしも誰が引き継ぐのかを円滑に決められるわけではありません。
話し合いで解決したいのに様々な理由で行き詰まり、相続手続きに支障が出る可能性があります。
揉める可能性が高いケースとしては主に以下の3つが挙げられます。
- めぼしい財産が不動産しかない:被相続人の財産のほとんどが不動産で、相続人間で分け難い
- 誰も不動産を相続したがらない・不動産の放置が懸念される:相続不動産が僻地にあり、引き継いで管理するのが困難
- 共有名義で相続が複雑化:被相続人以外の共有名義人との話し合いが面倒
それぞれのケースについて解説します。
ケース1:めぼしい財産が不動産しかない
被相続人に預金・現金がわずかしかなく、遺産のほとんどは土地・建物であるケースが該当します。
特に、被相続人の建物は分け難く、遺産分割をどうするかで揉めてしまう事態が想定されます。
(1)このままでは遺産分割が困難
被相続人に所有していた不動産がある場合、「夫婦で一緒に過ごした住居を引き継ぎたい」「私は長男なのだから、被相続人の土地・建物を引き継ぐのは当然だ」などと考える人も多いことでしょう。
しかし、不動産の他にめぼしい遺産が無ければ、法定相続人が複数いる場合、遺産を分割するのが困難です。
そのため、以下のような事態となり、相続人の間でトラブルが発生するおそれがあります。
- 不動産を相続した者だけが得する状況となり、相続できなかった者の不公平感は残り、「遺留分侵害額請求権」を行使される可能性がある
- 法定相続人全員の共有不動産にすれば遺産分割問題を簡単に解決できるものの、不動産の使用・管理で揉める可能性がある
遺留分侵害額請求権とは、法定相続人が遺留分(最低限確保されている相続分)を侵害された場合、侵害した者に対し、遺留分の侵害額に相当する金額を請求する権利です。
遺産が不動産のみで、特定の法定相続人だけが不動産を単独相続してしまうと、他の法定相続人から遺留分侵害額請求権を行使される場合があります。
法定相続人全員が平等かつ穏便に遺産分割を行うため、柔軟な対応が求められます。
(2)不動産売却を検討する
遺産が不動産のみの場合、不動産を売却すれば、売却により得られた現金を平等に分ける(換価分割する)ことが可能です。
不動産会社に相談・依頼すれば、担当者が不動産をさまざまな角度から調査し、売却価格の査定を行います。
その後、現れた買い手との売買契約を締結したり、場合によっては不動産会社が直接買い取ったりして、不動産の現金化が可能です。
相続不動産をお金に換えたら、法定相続人の間で平等に分配できます。
ただし、どうしても被相続人との思い出が残る土地・建物を売却したくないときは、別の方法による遺産分割を検討しましょう。
(3)引き継ぐ相続人が代償金を支払う方法もある
被相続人の遺産が不動産のみでかつ当該不動産を売却したくないなら、不動産の相続人が他の相続人に「代償金」を支払う方法もあります。
代償金は不動産を引き継いだ相続人の預金等で、他の相続人へ支払うことになるでしょう。
ただし、代償金を支払う場合にも、他の相続人と揉めるケースもあるでしょう。
代償金を支払うときにトラブルが発生した場合の解決策は以下の通りです。
- 代償金を支払いたいものの、預金が不足している:他の相続人は分割して支払う
- 他の相続人が代償金の支払い額に納得しない:不動産鑑定士に鑑定を依頼し、鑑定金額に従い支払い額を決めれば、公正な金額であると主張できる
- 法定相続人間で感情的となり話し合いが進まない:家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる
遺産分割調停は家庭裁判所に場所を移し、紛争当事者の和解を図る方法です。
調停では調停委員が当事者の言い分を聞き、和解案の提示等を行いながら、和解を進めていきます。
ケース2:誰も不動産を相続したがらない・不動産の放置が懸念される
被相続人の所有していた不動産が管理の大変な山林である場合、生前に使用していた農地・畑である場合、田舎にある古民家である場合などが該当します。
このような不動産を引き継ぐのは避けたいかもしれませんが、相続不動産を放置すればペナルティが課せられる場合もあります。
(1)相続登記をしないままでいるとペナルティが課される
相続不動産を放置すれば、引き継いだ相続人がペナルティを受けるおそれもあるので注意しましょう。
2024年4月1日から相続登記は義務化され、登記手続きの期限・違反した場合の罰則も定められました。登記手続きの期限は次の通りです。
- 2024年4月1日以降に不動産を相続:相続で不動産取得を知った日から3年以内
- 2024年4月1日以前に不動産を相続、未登記の状態:原則として2024年4月1日から3年以内
正当な理由がなく登記(名義変更)手続きをしなければ、10万円以下の過料が課せられてしまいます。
(2)土地の場合は相続土地国庫帰属制度を活用する
相続土地国庫帰属制度とは、2023年4月に創設された相続した土地の所有権・管理責任を国が引き取る制度です。
本制度の申請先は、引き取ってもらう土地を管轄する都道府県の法務局・地方法務局で、地方自治体は土地の情報提供等に協力する立場となります。
相続土地国庫帰属制度の申請の手順は次の通りです。
- 土地の相続人が、土地の所在する都道府県の法務局・地方法務局に承認申請(窓口または郵送で提出)
- 法務局担当官による書面調査
- 法務局担当官による実地調査
- 法務大臣・管轄法務局長による承認
- 申請者に承認・負担金通知
- 申請者は負担金を納付:負担金通知後30日以内
- 土地が国庫帰属
手続きの際は、土地の相続人以外の第三者へ影響を与えるかどうかも慎重に調査されます。
手続き完了までに半年〜1年程度かかる可能性があります。
まずは土地を管轄する都道府県の法務局・地方法務局と相談し、申請条件や負担金の額等を相談しつつ、慎重に手続きを進めていきましょう。
(3)被相続人が生前に売却する
被相続人が所有している不動産の放置を予期し、生前に売却しておくのも良い方法です。
被相続人自身が老人ホームに入所する等の措置を講じた後、次の対応を相談してみましょう。
- 自分の所有している住居、住居以外の建物:不動産会社に売却を相談
- 自分の所有している土地・山林:不動産会社に相談、山林の場合は森林組合への相談や山林バンク(全国の山林売買のマッチングサイト)の利用で買主を探す
森林組合とは、森林の保全・林業等の事業を共同で行う目的で設立された団体で、協同組合の一種です。
所有地を管轄する森林組合に相談すれば、取引実績が豊富なので安心して売却を依頼できます。
ケース3:共有名義で相続が複雑化
相続不動産が、被相続人とそれ以外の人との共有名義になっていたケースです。
そのまま相続すれば被相続人の持分のみが相続財産の対象となる他、今後の不動産売却・修繕に手間がかかる可能性もあります。
(1)不動産の売却やリフォームに支障が出るおそれも
共有名義の不動産を相続しても、持分を引き継いだ相続人は不動産全体の使用および管理が可能です。
ただし、持分を引き継いだ相続人が、不動産の売却や大規模なリフォームを希望する場合、共有名義人全員の同意が必要となります。
共有名義人に拒否されたら、思い通りに不動産を活用できなくなる場合もあるので注意しましょう。
(2)なるべく早く共有名義を解消しておく
共有名義の不動産は、被相続人の生前または相続時、速やかに共有名義を解消しておきましょう。
相続で所有者が変わってしまうと、たとえ親戚同士でも連絡が取れない状況となる可能性もあります。
相続の複雑化を避けるため、次のような方法で共有名義を解消しておくとよいでしょう。
- 被相続人の生前の段階:被相続人が共有名義人に代償金を支払い単独相続とする
- 相続開始時:相続人が共有名義人と不動産売却を話し合い、同意を得た後に売却する
共有名義人が代償金の支払いに納得しなかった、不動産売却を話し合っても同意に至らなかったという場合は、最終的に訴訟で解決する方法も検討してみましょう。
(3)共有物分割請求訴訟の提起も可能
共有名義を解消できないときの最終手段として、「共有物分割請求訴訟」の提起が可能です。
共有物分割請求訴訟とは、地方裁判所に対して不動産の共有状態の解消を求める訴訟です。
訴訟は共有名義人の同意がなくても提起できる他、適正な価格で現金化でき、裁判所が分割方法を決定するので、原告・被告共に納得しやすい点がメリットといえます。
ただし、訴訟提起はどこの裁判所でもよいわけではありません。
共有不動産を管轄する所在地、または被告の住所地を管轄する地方裁判所に限定されます。
また、訴訟を提起するときは主に次の書類も準備する必要があります。
- 訴状の正本・副本
- 収入印紙・郵券
- 固定資産評価証明書
- 不動産全部事項証明書(登記簿謄本)
訴訟提起や法廷での主張・立証の場合、弁護士に依頼するのが一般的です。
弁護士に依頼すれば有利に裁判を進められる可能性がありますが、費用がかかるので注意しましょう。
弁護士に依頼した場合の費用は数十万円〜100万円程度が相場です。
なお、訴訟の前段階で「共有物分割請求調停」を裁判所に申立ててもかまいません。
ただし、相手方(共有名義人)が和解に応じなければ結局、調停不成立となるので、あまり活用とされていない方法です。
まとめ
不動産相続で揉める可能性が高いケース、トラブルの解決方法などについて解説しました。
不動産をはじめとした遺産相続の協議は、感情的にならず冷静な判断のもとで合意を目指しましょう。
法定相続人の間のトラブルは調停や裁判で解決できますが、協議以上に手間や費用がかかります。
将来の不動産相続トラブルを回避するためには、被相続人の生前に不動産の売却や共有名義の解消を進めておくことが望ましいでしょう。