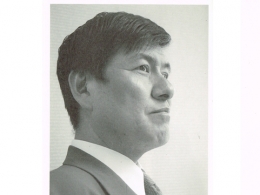相続財産調査とは・目的と方法についてわかりやすく解説

「故人がどれだけ遺産を残していたかわからない」「相続税が発生するのか非常に不安だ」などと感じている相続人は多いことでしょう。
被相続人(故人)の所有していた遺産がわからないと、相続人同士での遺産分割や、相続税の申告手続きも進まなくなってしまいます。
相続が開始されたら速やかに「相続財産調査」を行いましょう。
この記事では、相続財産調査のやり方や調査のポイント等について解説します。
相続財産調査とは何か
相続開始後、法律で相続財産調査の実施が義務付けられているわけではありません。
しかし、相続に際して被相続人の遺産や負債を正確に把握するためには、相続財産調査を行うことが必要になります。
(1)亡くなった人の財産を調べる方法
相続財産調査は、亡くなった人(被相続人)が所有する財産(金融資産・不動産資産)、負債(借金等)を調べる作業です。
生前に被相続人がエンディングノートに自身の財産を明記したり、財産の一覧表である「財産目録」を作成したりしている場合、それらが役に立つでしょう。
相続が開始されたら、基本的に相続人が調査を行いますが、弁護士や司法書士、行政書士のような士業専門家に調査を任せることも可能です。
(2)相続財産調査の目的
相続財産調査を行うのは、主に次のような判断や手続きを行うためです。
- 遺産や負債を正確に調査し、相続人が単純相続するか、限定承認するか、相続放棄するかを選択するため
- 遺産や負債を正確に調査し、複数の相続人へ公平な遺産分割を行うため
- 相続税が発生するか否かを確認し、申告・納税の手続きを行うため
被相続人の遺産や負債を調査し、遺産が多ければ、負債も含めて相続する単純相続を選ぶことでしょう。
しかし、遺産よりも負債が多いとわかったら、次のような方法を選べます。
- 限定承認:相続人全員の合意により、被相続人の遺産(プラスの財産)の範囲内で負債(マイナスの財産)を相続する方法
- 相続放棄:相続人が単独で被相続人の遺産や負債すべてを相続しない方法
また、相続財産調査を行えば、相続人の把握していなかった被相続人の遺産を発見できる場合があります。
そのため、遺産分割協議後に新たな遺産が発覚し、その配分を相続人全員で取り決める手間を軽減できます。
なお、相続財産調査により相続税が発生するか否かも判明するので、税務署から申告漏れを指摘される事態も回避できることでしょう。
相続財産調査の進め方
相続財産調査では被相続人の金融資産・不動産資産すべてを調査しなければいけません。
被相続人の残した財産の種別によって、調査の手順はそれぞれ異なります。
(1)預貯金や現金の調査
被相続人の自宅に現金がありそうな場合、金庫等を開錠し確認しましょう。
預貯金については、どのような金融機関(銀行等)を利用していたか、被相続人のカードや通帳を確認します。
カード・通帳が見つからないときは、次のような書類等も財産調査の手がかりとなります。
- 金融機関の郵便物
- エンディングノートや日記
- パソコン・スマートフォンの情報
金融機関の特定後、被相続人が亡くなった時点での残高を把握しましょう。
金融機関を特定しても通帳が見つからないときは、金融機関側に残高証明書の発行を申請します。
金融機関には次の書類等を提出しましょう。
- 残高証明書発行依頼書:用紙は金融機関窓口で取得、発行手数料は無料~900円程度と、各金融機関により異なる
- 被相続人の死亡の事実がわかる戸籍謄本(除籍謄本):被相続人の本籍地の市区町村役場で取得、手数料は1通450~750円
- 申請者の戸籍謄本:申請者の本籍地にある市区町村役場で取得、手数料1通450円
- 申請者の本人確認書類:運転免許証、パスポート等
- 申請者の実印および印鑑登録証明書:印鑑登録証明書は市区町村役場等で取得、手数料1通200~300円
なお、残高証明書だけではなく取引明細も取得すれば、取引履歴がわかり他の財産の調査にも役立ちます。
(2)負債に関する調査
被相続人の遺産(プラスの財産)だけではなく、負債(マイナスの財産)もしっかり調査しましょう。
遺産(プラスの財産)だけを把握し単純相続したものの、後日、債権者から被相続人の負債について指摘され、相続人が返済を迫られるおそれもあります。
次のような書類等がないか調査してみましょう。
- 金融機関や消費者金融等との契約書
- 請求書や督促状等の通知
- パソコン・スマートフォンに残った負債の情報
- エンディングノートや日記
- 預金通帳の取引履歴
なお、ローン・クレジット等の借入情報を管理する「信用情報機関」に、情報開示請求をすれば被相続人の借入先も把握できます。
信用情報機関は次の3社です。
いずれもインターネット・郵送で開示請求が可能です。
被相続人がお金を借りている金融機関・消費者金融の特定後、亡くなった時点での残高を把握するため、借入先に問い合わせて「借入金残高証明書」の発行を申請します。
(3)不動産の調査
被相続人の所有する不動産の「地番」と「家屋番号」の特定が必要です。
固定資産税の納税通知書や登記済権利証(登記識別情報)、エンディングノート等で確認が可能です。
①登記済権利証等が見つからないときは名寄帳で確認
手がかりが発見できなければ、相続不動産が所在する市町村役場に「名寄帳」を申請しましょう。
名寄帳は納税対象の不動産を所有者別に一覧でまとめた書類です。
ただし、複数の市区町村にわたり相続不動産がある場合、該当する市区町村役場にそれぞれ名寄帳を請求しなければいけません。
該当する市区町村役場には次の書類等を提出しましょう。
- 名寄帳申請書:用紙は市区町村役場窓口で取得、発行手数料は200~400円程度
- 被相続人の死亡の事実がわかる戸籍謄本(除籍謄本):被相続人の本籍地の市区町村役場で取得、手数料は1通450~750円
- 申請者の戸籍謄本:申請者の本籍地にある市区町村役場で取得、手数料1通450円
- 申請者の本人確認書類:運転免許証、パスポート等
- 郵送の場合は切手を貼り付けた返信用封筒
ただし、名寄帳の発行までに2〜3週間かかります。
②権利情報を確認する
相続不動産の地番・家屋番号が判明したら、不動産の権利情報(例:抵当権の有無等)を確認するため、法務局に登記事項証明書(登記簿謄本)を申請しましょう。
申請方法は下表の通りです。
| 申請方法 | 窓口・郵送 | オンライン |
| 申請先 | 最寄りの法務局 | 法務局「登記事項証明書等の請求にはオンラインでの手続が便利です」 |
| 申請費用 | 600円 | 500円(窓口受取480円) |
| 発行までの期間 | 即日 | 数日~1週間 |
③相続不動産の評価額を調査
相続不動産の必要情報を得られたら、評価額を調査しましょう。
複数の相続人と遺産分割するために評価額を算定するときは、次の評価方法があります。
- 実勢価格(取引価格):相続不動産の時価を評価する方法で、相続時に最も多く用いられている。国土交通省「不動産情報ライブラリ」で確認可能。
- 地価公示価格:国土交通省が毎年発表する土地の価格で、こちらも不動産情報ライブラリで確認できる。
- 路線価:道路に面する標準的な宅地の1㎡あたりの価額で、路線価が定められている地域の土地等を評価する。路線価が定められていない地域は、市区町村の「評価倍率表」で評価。国税庁「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」で確認可能。
- 固定資産税評価額:固定資産課税台帳に記載された固定資産税の課税基準となる土地・建物の評価額。市区町村役場から通知される固定資産税の納税通知書「課税明細書」、固定資産税評価証明書で確認可能
なお、相続税の申告のため評価額を算定したいとき、土地は路線価・倍率方式、家屋は固定資産税評価額で評価します。
より正確に評価額を出したいならば、税理士等のような専門家へ任せた方がよいでしょう。
(4)有価証券に関する調査
被相続人が有価証券を保有しているかどうかについても調査しましょう。
株券の他、取引報告書・配当金支払通知書のような証券会社の通知、預金通帳の取引履歴やエンディングノート等から確認が可能です。
有価証券の有無が確認できない場合は、証券保管振替機構(有価証券取引を管理する機関)に問い合わせましょう。
開示請求をするときは、次の書類を揃えて証券保管振替機構に郵送します。
- 開示請求書:証券保管振替機構ホームページより取得可、開示費用は1件6,050円(2件目以降:1件あたり1,100円加算)
- 被相続人の本人確認書類:運転免許証、パスポート等
- 被相続人の死亡の事実がわかる戸籍謄本(除籍謄本):被相続人の本籍地の市区町村役場で取得、手数料1通450~750円
- 申請者の印鑑登録証明書または住民票:市区町村役場等で取得、手数料1通200~300円
- 申請者の戸籍謄本:申請者の本籍地にある市区町村役場で取得、手数料1通450円
- 申請者の本人確認書類:運転免許証、パスポート等
- 郵送の場合は切手を貼り付けた返信用封筒
開示までの期間は2〜3週間かかります。
開示請求で証券会社が特定できた場合、各証券会社の指示に従い有価証券の残高を確認しましょう。
相続財産調査を行うポイントについて
相続財産調査に法定された調査手順はないものの、効率的な調査や判明した財産を正確に記録するにはコツがあります。
以下の3つのポイントを押さえ、調査を進めていきましょう。
(1)ポイント1:財産目録を作成する
事前に財産目録を準備し、チェックリストとして活用すれば、被相続人の遺産や負債を正確に把握できることでしょう。
財産目録とは、被相続人の財産の種類や負債の状況を一覧表にまとめた書類です。
相続税を申告するときは必要書類となります。
なお、遺産分割協議をしたときに作成する、「遺産分割協議書」の添付書類として活用が可能です。
財産目録を相続人が一から作成する必要はなく、次のように無料で雛形を取得できます。
- 裁判所:家庭裁判所で使う書式
- bizocean:「財産目録」の書式テンプレート・フォーマット
(2)ポイント2:調査は預貯金から開始する
相続財産調査は、預貯金・現金→負債→不動産の調査→有価証券等という流れで進めた方がよいでしょう。
とくに預貯金の取引履歴が把握できれば、ローンや不動産、有価証券等の財産・負債を調査する手がかりとなります。
相続財産調査に法定された期限はないものの、次のような期限に注意が必要です。
- 限定承認・相続放棄:相続の開始があった事実を知ったときから3か月以内
- 相続税の申告・納付:相続の開始があった事実を知った日の翌日から10か月以内
(3)ポイント3:財産に関する保管場所を効率よく調べる
相続財産調査の参考となる書類の保管場所を迅速に確認しましょう。
被相続人が財産や負債に関する書類を保管する場所には、ある程度傾向があります。
たとえば被相続人の金庫やデスク、棚・引き出し、押し入れ、仏壇等があげられます。
銀行の貸金庫の有無も、忘れずに確認が必要です。
その他、パソコンやスマートフォンに財産情報を記録している場合もあるでしょう。
まとめ
正確な遺産分割や相続税の申告・納付には、相続財産調査が必要です。
ただし、被相続人の遺産や負債が多い場合、調査は難航する場合もあるでしょう。
相続人だけでは調査が難しいと感じたら、速やかに専門家へ相談することをおすすめします。