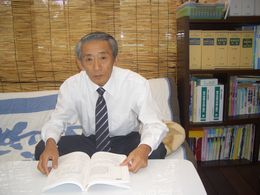遺留分減殺請求とは?改正民法で遺留分侵害額請求に変更された内容を解説

故人の遺した遺言書を見たところ「一部の相続人に遺産が集中し、自分の遺留分が侵害されていた」「自分の遺留分を取り戻したい」などと考えている方もいらっしゃるでしょう。
そのようなとき、自分の遺留分(兄弟姉妹以外の法定相続人に最低限保障された相続分)を取り戻すために、「遺留分減殺請求」という方法があります。
2019年7月1日に施行された改正民法で、この遺留分減殺請求は「遺留分侵害額請求」へと名称が変更されています。
この記事では、遺留分減殺請求の特徴と、遺留分侵害額請求との違い等について解説します。
遺留分減殺請求について
遺留分減殺請求は改正民法(2019年7月1日施行)以前の、自らの遺留分(最低限度の遺産を受け取れる権利)を確保するための制度でした。
遺留分減殺請求の特徴について説明します。
(1)遺留分減殺請求とは
遺留分減殺請求とは、遺留分を下回る額の遺産しか取得できなかった、または遺産をまったく取得できなかった相続人が、遺産を多く受け取った人(遺留分を侵害した人)に対して行う請求です。
被相続人(遺言者)が遺言書を作成していた場合、遺産の取得に関して、特定の相続人に偏った遺言内容である場合もあります。
しかし、遺留分を下回る遺産しか受け取れなかった相続人は、遺留分減殺請求を行使して、自分の遺留分を取り戻せる可能性があります。
(2)遺留分減殺請求の対象
遺留分減殺請求を行使できる人物と、請求の対象となる遺産は次の通りです。
- 遺留分減殺請求を行使できる人物:被相続人の配偶者、直系卑属(子や代襲相続人)、直系尊属(親等)が対象
- 遺留分減殺請求の対象となる遺産:侵害された遺産自体
被相続人の兄弟姉妹は遺留分を主張できない(民法第1042条)ので、遺留分減殺請求も認められません。
また、遺留分減殺請求では対象となる遺産を特定後、その遺産自体を取り戻すための請求が必要です。
たとえば、取り戻す遺産が不動産の場合、遺留分減殺請求の対象となるのは不動産に限定されます。
つまり、不動産の代わりに金銭で取り戻すという方法は認められていませんでした。
不動産のような分割が難しい財産は、遺留分を侵害した人との共有になります。
不動産を対象に遺留分減殺請求が行われた場合、原則として現物返還で解決しなければいけません。
そのため、共有物をスムーズに活用できず、共有者とのトラブルに発展するケースもありました。
改正民法により遺留分減殺請求から遺留分侵害額請求へ変更
遺留分減殺請求を行うと、預貯金のような金融資産の取り戻しは容易であるものの、不動産の場合は遺留分を侵害した相手との共有になってしまいます。
そこで遺留分侵害の問題を柔軟に解決できるよう、改正民法で「遺留分侵害額請求」に改められました。
(1)遺留分減殺請求と遺留分侵害額請求との違い
遺留分減殺請求と遺留分侵害額請求の特徴を比較してみましょう。
| 比較対象 | 遺留分減殺請求 | 遺留分侵害額請求 |
| 請求対象 | 侵害された現物財産の返還 | 侵害された遺留分相当額の金銭支払い |
| 生前贈与の範囲 | 生前贈与が特別受益に該当すれば、すべて遺留分の算定対象 | 生前贈与が特別受益に該当すれば、被相続人の死亡から過去10年間に取得した財産が遺留分の算定対象 |
遺留分算定時、算定の対象となる財産には生前贈与(被相続人の存命中、自分の財産を他者に贈与する方法)も含まれます。
表のように遺留分減殺請求と遺留分侵害額請求では、遺留分算定のため財産に加える生前贈与の範囲が異なります。
ただし、次のケースでは遺留分減殺請求も遺留分侵害額請求も、生前贈与の範囲は変わりません。
- 相続人以外が受けた生前贈与:過去1年分のみの生前贈与
- 生前贈与の贈与者・受贈者双方が、遺留分権利者に損害を加えると知っていながら生前贈与をした:すべての生前贈与が遺留分算定の対象
(2)具体例を用いた比較
具体例をあげ、遺留分減殺請求と遺留分侵害額請求の方法を比較してみましょう。
(例)被相続人が亡くなり遺産は1億円あり、生前贈与・債務はない。法定相続人は子A・Bがいる。
- 遺産の内訳:不動産(相続開始時の時価8,000万円)、預貯金(2,000万円)
- 子A:不動産を相続
- 子B:預貯金を相続
被相続人の子の遺留分割合は1/2(A・Bそれぞれ1/4)なので、次のように遺留分を計算します。
- 子A:1億円×1/4=2,500万円
- 子B:1億円×1/4=2,500万円
Bは預貯金2,000万円しか遺産を取得できない状態となっており、500万円分の遺留分侵害が発生しました。
【遺留分減殺請求の場合】子A・Bは不動産を共有する
BがAに対し遺留分減殺請求を行えば、Bは500万円分(=16分の1)の相続不動産の共有持分を取得します。
【遺留分侵害額請求の場合】子BはAに金銭の支払いを請求する
Bが遺留分侵害額請求を行うと、Aは500万円を支払わなければいけません。
ただし、Aは相続不動産の完全な所有権を有しているので、Bとの共有状態は発生しないことになります。
遺留分侵害額請求の流れ
遺留分侵害額請求を行う場合、遺留分を侵害している相手といきなり裁判で争うわけではありません。
一般的には次のような方法をとり、問題の解決を目指します。
- 遺留分を侵害している相手と話し合う
- 「内容証明郵便」で遺留分侵害額を請求する
- 家庭裁判所に「遺留分侵害額の請求調停」を申し立てる
- 裁判所に「遺留分侵害額請求訴訟」を提起する
それぞれの請求方法について説明します。
(1)第1段階:遺留分を侵害する相手との交渉
侵害された本人と侵害した相手が交渉する場合、とくに必要な書類は法定されていません。
交渉するときは、遺言書の他に被相続人の遺産に関する証明書等を提示し、冷静に遺留分侵害の問題解決を図りましょう。
相手方と合意したら義務ではないものの、「合意書」を作成した方がよいです。
合意書を作成する場合、主に次のような合意内容を明記します(書式自由・パソコンで作成可)。
- 被相続人氏名・生年月日・死亡日
- 相続人それぞれの氏名
- 交渉に合意した旨
- 遺留分侵害額相当額の金銭を支払う旨
- 金銭の支払い日・支払い方法
- 被相続人の遺産(不動産・金融資産)
- 新たな遺産が発見された場合の分割方法
- 合意書に定めた内容以外、何らの債権債務も存在しないことを相互に確認する旨
合意書は複数作成し、当事者が署名捺印後それぞれ1通ずつ大切に保管しましょう。
(2)第2段階:内容証明郵便の送付
交渉が不調に終わった場合、内容証明郵便を利用し、侵害した相手方に「催告書」を送付します。
催告書には遺留分が侵害されている事実や遺留分侵害額相当額、支払い期日、支払わない場合は法的措置に移行する旨を明記しましょう。
なお、内容証明郵便で催告書を送付する場合、字数・行数制限があります。
縦書き・横書きによってそれぞれ制限が異なります(句読点等の記号も1文字)。
- 縦書き:1行20文字以内で1ページ26行以内
- 横書き:1行20字以内で1ページ26行以内、1行13字以内で1ページ40行以内、1行26字以内で1ページ20行以内のいずれか
催告書は同じ内容で3通(侵害した相手方への送付用、他に差出人用・郵便局の保存用)作成しましょう(送付費用:約1,420円)。
(3)第3段階:遺留分侵害額請求調停を申し立てる
内容証明郵便を送付しても相手方が支払いに応じない場合、相手方の住所地または当事者の合意した家庭裁判所に申立てが可能です。
必要書類は下の表の通りです。
| 必要書類 | 内容 | 取得方法 |
| 申立書等 | 調停申立書、土地遺産目録、建物遺産目録、現金・預貯金・株式遺産目録 | 裁判所の公式サイト等で取得可能 |
| 被相続人・紛争当事者との関係がわかる書類 |
・死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 ・相続人全員の戸籍謄本 |
・本籍地の市区町村で取得 ・手数料:1通450~750円 |
| 被相続人の遺産に関する証明書 | 不動産登記簿謄本や固定資産評価証明書、預貯金通帳コピー・残高証明書等 |
・不動産登記簿謄本:法務局で取得(1通480~600円) ・固定資産評価証明書:市区町村で取得(1通300円) |
| 遺言書が作成されている場合 | 遺言書または遺言書の検認調書謄本コピー |
・被相続人が自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合は法務局で取得 ・公正証書遺言の場合は公証役場で取得 |
| その他 | 収入印紙・連絡用の郵便切手 |
・収入印紙1,200円分をコンビニ等で取得 ・連絡用の郵便切手の金額は裁判所に要確認 |
また、追加書類が必要となるケースもあるので、家庭裁判所の指示に従い、書類の作成・収集を行いましょう。
(4)第4段階:遺留分侵害額請求訴訟を提起する
調停が不調に終わったときは、地方裁判所または簡易裁判所(請求金額140万円以下の場合)に訴訟提起が可能です。
裁判所に提出する「訴状」は2部作成し、当事者(原告・被告)の氏名・住所・郵便番号送達場所、請求の趣旨・原因等を明記します。
訴状は裁判所に用紙が用意されておらず、遺留分を侵害された本人が作成するか、弁護士または司法書士に訴状作成を依頼する必要があります(ただし、司法書士は訴訟代理人になれない)。
その他に訴訟提起の際は遺言書や、証拠書類(不動産登記簿謄本や固定資産評価証明書、預貯金通帳コピー・残高証明書等)、収入印紙・連絡用の郵便切手を準備します。
遺留分で相続人が揉めないための方法
被相続人も相続人も、遺留分の問題で揉めないよう柔軟に対応し、相続トラブルを未然に防ぐ努力が必要です。
(1)被相続人は遺言書作成時、相続人への公平な分配を心がける
被相続人は遺言書を作成する場合、相続人同士で遺留分侵害をはじめとした相続トラブルが起きないよう、公平な遺産の配分に努めましょう。
- 相続人から不満が出ないよう、遺産を分ける方法について工夫する(遺言書の作成前、相続人となる方々にどのような遺産が欲しいか聞いておく等)
- 特定の相続人に生前贈与をしていたかどうか慎重に確認し、生前贈与をしていた場合は、贈与していなかった相続人へ多めに遺産を譲渡する
慎重に遺言書を作成すれば、相続人それぞれが円満に遺産を取得できることでしょう。
(2)遺産分割協議を行い公平に分割する方法も可能
遺言書の内容が不公平で、相続人の一部から不満が出たら、相続人全員の合意で「遺産分割協議」を行い、あらためて分割内容を取り決めてもかまいません。
協議を行い相続人全員が納得したなら、深刻な相続トラブルに発展する事態を回避できます。
ただし、次のようなケースでは遺言書と異なる遺産分割協議ができません。
- 相続人以外の受遺者がいる:受遺者の権利を相続人が一方的に奪ってはいけないため
- 遺言書で遺産分割を禁止している:相続開始のときから最長5年間は遺産分割ができない
まとめ
遺留分減殺請求は改正民法(2019年7月1日施行)により、名称と請求内容が変更されている点に注意しましょう。
改正後の遺留分侵害額請求では、侵害された遺留分相当額の金銭支払いを請求できます。
そのため、現物返還を目的とする遺留分減殺請求より、スムーズに遺留分の問題の解決を図れます。
遺留分に関して不安や悩みがある場合、速やかに弁護士や司法書士、行政書士などの士業専門家へ相談することをおすすめします。