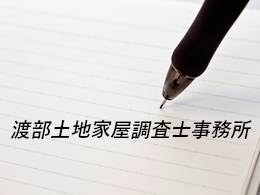遺産相続で他の相続人と関わりたくない!対処方法を解説

被相続人が死亡し、相続が発生したものの「他の相続人と一切関わりたくない」「他の相続人と遺産について話し合いたくない」「他の相続人と顔を合わせるくらいなら、遺産相続の権利を放棄してもかまわない」などと、考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、遺産相続の話し合いを無視すると、さらに他の相続人との亀裂が深まる事態や、相続手続きが進まなくなる可能性もあります。
この記事では、他の相続人と関わりたくないときの適切な対処方法について解説します。
遺産相続で他の相続人と関わりたくない理由と注意点
被相続人の遺産や負債を引き継ぐ相続人が一人だけとは限りません。
複数の相続人が存在していて、もともと特定の相続人と仲が悪かったり、他の相続人と疎遠になっていたりしているケースは珍しくないでしょう。
ただし、他の相続人と関わりたくないからと、遺産相続の話し合いを無視していると、予想外のトラブルが発生する可能性もあります。
(1)他の相続人と関わりたくない理由はいろいろある
他の相続人と関わりたくない理由は人それぞれです。
- もともと兄弟姉妹で仲が悪く、交流はほとんどない
- 結婚や独立で家を出て以来、親族とはすっかり疎遠になった
- 被相続人に離婚歴があり、前婚の元配偶者との間に子どもがいる
特に前婚の元配偶者の子どもがいるときは、日ごろから交流を避けている場合も多いことでしょう。
被相続人の元配偶者は相続人とならないものの、子どもには相続権があります。
被相続人の遺言書が残されていない場合、相続人全員で遺産分割協議を行い、被相続人の遺産を分ける必要があります。
この場合、関わりたくなくても、元配偶者との子どもを遺産分割協議に参加させなければいけません。
(2)遺産相続の際に無視は禁物
他の相続人と関わりたくないからと、遺産分割協議への参加を拒否していると、他の相続人と深刻なトラブルに発展する可能性があるので注意しましょう。
遺産分割協議で遺産を分けるときは相続人全員の参加が必要であり、相続人が一人でも欠けた状態での協議は無効となります。
そのため、以下のような態度のままでは、遺産分割協議が進まなくなってしまいます。
- 他の相続人と関わりたくないからと、遺産分割協議の申し出を拒否している
- 自分は遺産分割協議をする気があるものの、嫌っている特定の相続人を協議に参加させようとしない
他の相続人と関わりたくなくても、何らかの対応をとらなければ、相続人同士で相続争いが発生したり、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申立てられたりする可能性があります。
他の相続人とのトラブルを避け、相続手続きに手間をかけたくないのであれば、たとえ関わりたくなくとも相続人全員で遺産分割協議を進めていきましょう。
相続人と関わりたくないなら相続放棄をする
「他の相続人と関わるくらいなら遺産を相続したくない」「相続人としての権利を放棄してもかまわない」などと考えている場合は、「相続放棄」を検討しましょう。
相続放棄が認められれば、遺産相続で他の相続人と関わる必要がなくなります。
(1)相続放棄とは?
相続放棄とは、被相続人の遺産を引き継ぐ権利、そして義務を一切放棄する手続きのことです。
相続に関しては、はじめから相続人とならなかったものとみなされるので、遺産分割協議に参加する必要はありません。
ただし、相続放棄が認められると、被相続人の負債(借金)を引き継がずに済むものの、被相続人の遺産も一切相続できなくなります。
また、相続放棄するときは必要書類を揃え、家庭裁判所に申述しなければなりません。
(2)相続放棄のメリット・デメリット
相続放棄が家庭裁判所から受理されると、はじめから相続人とならなかったものとみなされます。
そのため、その他の相続人から遺産分割協議に参加するよう求められても、相続放棄を理由に参加を拒否できます。
また、被相続人が多額の負債(借金)を残していた場合、相続放棄をした人は債権者から返済するように請求された場合でも、相続放棄を理由に返済を拒否することが可能です。
一方、被相続人の預貯金・不動産等のプラスの遺産を一切引き継げなくなるという点には注意しましょう。
ただし、相続放棄をした人が被相続人の生命保険(死亡保険)の保険金受取人になっているときは、たとえ相続放棄をしても保険金が受け取れます。
なぜなら保険金は、被相続人の財産ではなく保険金受取人の固有の財産となるからです。
相続放棄の手続きの手順と必要な書類
相続放棄は「他の相続人と関わりたくない」という理由であっても申述が可能です。
ただし、相続放棄には期限があり、自己のために相続の開始があった事実を知ったときから3か月以内に行わなければいけません。
相続放棄の手続きの手順と、手続きに必要な書類について説明します。
(1)相続放棄の手続きの手順
相続放棄の手続きの手順は以下の通りです。
- 被相続人の遺言書の有無を確認:遺言書があれば遺言内容に従い遺産を引き継ぐので、基本的に他の相続人との協議は不要となる。遺言内容に問題がなければ相続人として遺産を引き継いでもよい。
- 遺言書がなければ、遺産分割協議が必要かを確認:遺言書がないときは財産調査を行ったうえで、関わりたくない相続人と協議してまで遺産を得る必要があるのか、慎重に考慮する。
- 相続放棄の準備を開始:相続放棄を決めたら、相続放棄申述書等の必要書類の作成・収集を行う。
- 家庭裁判所に申述する:法定された期限内に被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ、必要書類を提出する。家庭裁判所に直接持参するか郵送してもよい。
- 家庭裁判所が内容を確認する:申述内容を確認し、場合によっては「照会書」が家庭裁判所から送付され質問への回答を要求されたり、資料の追加を求められたりする可能性がある。
- 家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届く:申述に問題がなければ家庭裁判所は通知書を自宅に送付し、手続きが完了する。
家庭裁判所に必要書類を提出後、相続放棄申述受理通知書が届くまでに、3週間〜1か月程度かかります。
(2)相続放棄に必要な書類
相続放棄の申述を行うときは、主に以下の書類を家庭裁判所に提出する必要があります。
| 書類 | 取得方法 | 手数料 |
| 相続放棄申述書 | 裁判所の公式サイトまたは家庭裁判所の窓口等で取得する | 無料 |
| 被相続人の住民票除票または戸籍附票 |
・住民票除票:被相続人の住所地の市区町村役場で取得 ・戸籍附票:被相続人の本籍地の市区町村役場で取得 |
・住民票除票:1通約200円 ・戸籍附票:1通約300円 |
| 死亡記載のある被相続人の戸籍謄本 | 被相続人の本籍地の市区町村役場で取得 | 1通約450円 |
| 申述人の戸籍謄本 | 申述人の本籍地の市区町村役場で取得 | 1通約450円 |
| 収入印紙 | 郵便局・コンビニ等で取得 | 800円分 |
手続き完了後、相続放棄を他の相続人や被相続人の債権者等に主張するため、相続放棄をした旨の証明書も取得しておいた方がよいでしょう。
「相続放棄申述受理証明書」を取得するには、家庭裁判所窓口に申請用紙があるので、申請用紙に必要事項を記入し、1件につき150円分の収入印紙を添付します。
- 郵送申請の場合:返信用の切手を同封
- 窓口申請の場合:印鑑・受理通知書・本人確認書類(運転免許証等)を持参
いずれかの方法で申述を受理した家庭裁判所に申請しましょう。
相続放棄を行うときの注意点について
相続放棄は他の相続人の同意を要せず、単独で申述が可能です。
ただし、申述人が相続放棄を行う前に注意しなければいけない点もあります。
相続放棄を行うときの主な注意点について説明します。
(1)相続放棄は撤回できない
いったん相続放棄が受理された以上、たとえ自己のために相続の開始があった事実を知ったときから3か月以内であっても、撤回は認められません(民法919条第1項)。
そのため、期限内に相続財産の状況を調査しても、相続を承認するか放棄するかを判断できる資料が得られないときは、「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」を行いましょう。
申し立てを家庭裁判所が受理すれば、1〜3か月程度の期間の伸長が可能です。
なお、相続放棄の申述が受理されるまでの間であるなら、自由に取り下げができます。
一方、以下のようなやむをえないケースであれば相続放棄の「取消」が可能です。
- 詐欺や強迫を受け、やむなく相続放棄をした
- 未成年者や成年被後見人等が単独で相続放棄をした 等
(2)相続放棄を行うと付き合いのない親戚とトラブルに発展するケースも
相続放棄は自分一人の判断で行うことが可能ですが、以下のような事態になると、他の相続人との間でトラブルになる可能性があるので注意しましょう。
- 相続放棄を理由に、現に占有している被相続人の遺産を放置している
- 相続放棄により他の相続人の遺産分割割合や、相続人の地位に影響が出た
例えば相続放棄をした人が、被相続人の所有していた住居に住んでいる場合、引き継ぐ相続人または相続財産清算人に住居を引き渡すまで、しっかりと管理しなければいけません。
そのため、相続放棄したからという理由で住居の管理を怠り、それが原因で破損・焼損した場合は住居の管理責任を問われてしまいます。
また、相続放棄により他の相続人の遺産分割割合が大きく変化し、相続放棄をした人の次順位であった親族(例:被相続人の子どもが放棄したので、祖父母が相続人となった等)が繰り上がる可能性もあります。
相続放棄という予想外の事態に他の相続人が困惑する場合もあるので、事前に他の相続人へ相続放棄する旨を通知しておきましょう。
まとめ
遺産相続で他の相続人と関わりたくないときは、相続放棄を行うことを検討してもよいでしょう。
ただし、他の相続人へ知らせずに相続放棄を行った場合、深刻なトラブルに発展する場合があるので注意が必要です。
相続放棄を検討する際は、他の相続人に与える影響についても十分に考慮しましょう。
相続放棄に関して不安な点や疑問点がある場合は、事前に弁護士や司法書士、行政書士などの士業専門家に相談するとよいでしょう。