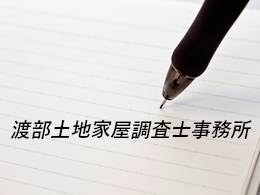相続土地国庫帰属制度とは?制度の内容や手続き方法を解説

相続が発生し被相続人の土地を引き継いだものの、「土地が自宅より遠くてとても管理しきれない」「相続した土地は不要なので誰かに管理してもらいたい」などと、考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
被相続人の所有していた土地を相続しても、十分に管理できないまま放置してしまうと、さまざまなトラブルが発生するおそれもあります。
土地の管理が困難で、手放したいけれど、売却が難しいという場合に役立つのが相続土地国庫帰属制度です。
この記事では、相続土地国庫帰属制度の概要、制度を活用するメリット、手続きの流れと必要書類、制度を利用する場合の負担金額などについて解説します。
相続土地国庫帰属制度とは?
相続土地国庫帰属制度は、先祖代々からの相続が重なり権利関係の複雑化や、所有者不明の土地が年々増加している日本の土地問題を解決するため、2023年4月に創設された制度です。
本制度の内容と利用するメリットについてみていきましょう。
(1)相続土地国庫帰属制度は相続土地の引き取り制度
相続土地国庫帰属制度は、相続人が引き継いだ土地の所有権・管理責任を国が引き取る制度です。
相続した土地の管理に行き詰まり放置されるケースが多いため、所有権が明確なうちに国の管理として土地の再利用を促し、新たな所有者のもとで活用することがこの制度の主な目的です。
相続土地国庫帰属制度を利用するときは、当該土地を管轄する都道府県の法務局・地方法務局が申請先となります。
一方、地方自治体は土地の情報提供などに協力する立場となります。
(2)相続土地国庫帰属制度のメリット
相続土地国庫帰属制度を利用する主なメリットは以下の通りです。
- 宅地の他に農地や山林も引き取り対象
- 購入者が現れなかった土地でも引き取り可能
- 国の管理下に置かれる
相続した宅地や農地・山林であっても制度を利用することが可能なので、農地・山林を相続して困っている相続人も安心して申請できます。
また、土地が辺鄙な場所にあると土地の購入希望者が現れる可能性はかなり低いことでしょう。そのような土地であっても条件さえ合えば、国に引き取ってもらえます。
引き取られた土地は国が責任を持って管理するので、先祖代々守ってきた土地が荒れ地となる事態を避けられるでしょう。
当該土地の再利用に関しても国の審査を経るので、引き取られた土地は有効活用されることが期待できます。
相続土地国庫帰属制度の手続きの流れと必要書類
相続土地国庫帰属制度を申請する場合、書類提出後は法務局側による慎重な調査が実行されます。
相続土地国庫帰属制度の申請手順や必要書類をみていきましょう。
(1)相続土地国庫帰属制度の手続きの流れ
相続土地国庫帰属制度の申請から国庫帰属に至るまでの流れは以下の通りです。
- 土地の相続人等が、土地の所在する都道府県の法務局・地方法務局に承認申請(窓口または郵送で提出)を行う
- 法務局担当官が書面調査を行う
- 法務局担当官が実地調査を進める
- 法務大臣・管轄法務局長の承認を受ける
- 申請者に承認・負担金を納付する旨の通知が届く
- 申請者が負担金を納付する(負担金の通知後30日以内)
- 申請した土地が国庫に帰属する
相続土地国庫帰属制度の申請をすれば、すぐに受理されて、相続した土地を国が引き取るわけではありません。
国庫に帰属するまでには半年〜1年程度かかる可能性もあります。
(2)手続きで必要な書類
申請の際にかかる費用・必要書類は以下の通りです。
なお、遺贈または遺産分割協議によって土地を取得したとき、それぞれ必要な書類も異なります。
| 必要書類:共通 |
|
| 必要書類:遺贈によって土地を取得した場合 |
|
| 必要書類:遺産分割協議によって土地を取得した場合 |
|
| 任意で添付する書類 |
|
申請する際、土地の図面はもちろん写真撮影も必要です。
法務局担当者は実地調査の前に書面調査を行うので、土地に建物が建っていないか、土地に一定の勾配・高さの崖がないかなどを確認しやすいように撮影しましょう。
遺言書で土地を引き継ぐ人が指定されていれば、基本的に指定された本人が相続します。
申請するときは遺言書を準備しましょう。
一方、遺言書は残されているけれど、土地を相続したくないという場合、相続人全員の同意があれば遺産分割協議で決めてもかまいません。
遺産分割協議書で引き継ぐ人を決めた場合は、遺産分割協議書や相続人全員の印鑑証明書等が必要になります。
相続土地国庫帰属制度を利用する場合の負担金額
申請承認後は、土地管理費相当額の負担金(10年分)を納付する必要があります。
土地の種類に応じてかかる負担金額は下の表の通りです。
| 土地の種類 | 負担金額 |
| 宅地 |
原則20万円 ただし、市街化区域、用途地域が指定されている地域は面積に応じて算定 (例)
|
| 田畑 |
原則20万円 ただし、市街化区域、用途地域が指定されている地域、農用地区域内等は面積に応じて算定 (例)
|
| 森林 |
面積に応じ算定 (例)
|
|
その他 ※原野や雑種地等 |
一律20万円 |
面積に応じた負担金額の算定方法は、法務省が以下のページで公開している「負担金額の自動計算シート」を用いれば簡単に計算できます。
相続土地国庫帰属制度を使えないケースについて
引き継いだ土地がどのような状態のものでも、国が必ず引き取るわけではありません。
土地が申請できないケースに該当すれば申請はそもそもできず、問題のある土地に該当すれば国からの承認も受けられないので注意しましょう。
(1)申請できないケース
法務局へ相続土地国庫帰属制度の申請を行う前に、以下のケースに該当しないか確認が必要です。
- 建物があった
- 担保権(抵当権等)や使用収益権が設定されている
- 他人の利用が予定されていた
- 土壌が汚染されていた
- 境界が明らかでない、所有権の存否や範囲について争いがある
申請できないケースに該当するときは、まずは当該問題を解決してから、申請を行わなければいけません。
土地に建物があったり担保権が設定されていたりする状態である場合、土壌が汚染されていた場合はその除去を行いましょう。
また、他人の利用が予定されている場合は、代替地等を用意したり、第三者との土地に関する争いを解消したりする必要があります。
(2)承認を受けられないケース
無事に申請を行うことができても、まだ安心はできません。以下のようなケースに該当すれば不承認となってしまいます。
- 一定の勾配・高さの崖がある
- 有体物が地上にあった
- 除去しなければいけない有体物が地下にある
- 隣接する土地の所有者等と争訟をしないと引き取れなかった
- その他、管理に過分な費用・労力がかかる
法務局担当官が実地調査を行う以上、申請者の確認していなかった不承認事由が発覚する可能性もあるので注意しましょう。
例えば、一見不承認事由に該当するものが見当たらなくとも、除去しなければいけない有体物が地下にあるおそれもあります。
除去しなければいけない有体物とは、主に産業廃棄物や瓦・管等が該当します。何が埋まっているかは被相続人(以前の所有者)も、土地を引き継いだ相続人もよくわからない場合があるでしょう。
ただし、除去しなくても土地の通常の管理に問題がない場合(例:広大な土地の隅に小規模な配管があった等)は、不承認事由に当たりません。
(3)申請に不安を感じたら法律の専門家へ相談しよう
相続土地国庫帰属制度の申請手続きは複雑で、相続人だけの力では難しい面があります。
申請前に「手続きがよくわからない」「相続した土地を国に引き取ってもらえるのか不安だ」と感じたら、弁護士や司法書士のような専門家に相談してみましょう。
- 本制度の申請手続きに関して→司法書士
- 土地に関するトラブル→弁護士
申請手続きについては、司法書士が有益なアドバイスやサポートを提供します。
また、他の土地所有者と境界線トラブルや争訟になっている等の場合、弁護士を代理人にすれば、円満に問題を解決できる可能性が高まります。
弁護士は対立している相手との交渉役となる他、裁判で解決するときは訴訟手続き・訴訟代理人も任せられます。
専門家への相談料は、基本的に30分5,000円程度(無料で受け付けている事務所もあり)です。
まとめ
2024年4月1日以降、相続で被相続人の土地を引き継いだ相続人には登記が義務付けられました。
土地等の不動産を引き継いだ相続人は、その取得を知った日から3年以内に、登記手続きを済ませなければいけません。
また、義務化は2024年3月31日以前に相続した未登記不動産へも適用されます(施行日から3年以内が期限)。
期限内に相続登記をしなければ、ペナルティを受けるおそれがあるので(10万円以下の過料等)、手続きに焦る相続人は多くなる可能性があります。
土地を相続したものの「自分の力では土地を管理できない」などとお悩みでしたら、相続土地国庫帰属制度の活用を検討しましょう。
この制度を利用すれば、相続した土地を管理する重い負担を回避することができます。